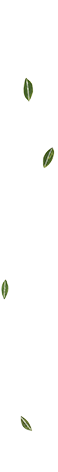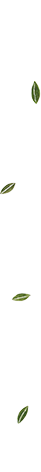2019年の金価格の歴史的上昇の背景にあるのは、世界中で日替わりメニューのごとく有事が勃発して投資マネーが安全資産である金に流れ込んでいること、そして、マイナス金利で「利息を生まない=ゼロ金利」の金がハイイールド(高利回り)の運用先とまで言われて選好されるという珍現象が起きていることだと、前回お話しました。 そこで今回は、こうした先行き不透明な時代の“資産防衛策”としての金について解説したいと思います。
金が株式のように“底抜け”しない理由 |
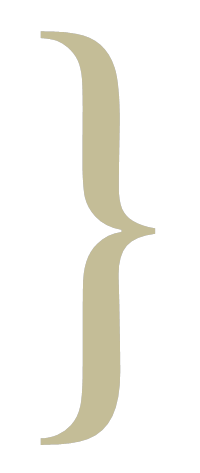 |
 |
金のセミナーに登壇すると、参加者の方から質問を受ける機会があります。少し前までは「金価格はどこまで上がりますか?」という質問が圧倒的多数を占めていたのですが、最近多いのが「金価格は下がるとしたらどこまで下がるのですか?」というものです。 実感としては、8割方この手の質問です。 そして、これに対して私が「金は底抜けしないんですよ。」と言うと、皆さん「えっ、そうなんですか?」と熱い視線を返してきます。
では、金はなぜ底抜けしないのでしょうか。そこには金の生産コストが大きく影響しています。
金を掘るには採掘コストがかかります。平均すると1オンスあたり1000ドル弱ほどです。しかし、金鉱山によってコストには差があり、全体の2割くらいの金鉱山では1オンスあたり1000~1200ドルと高めなのです。 金の採掘は企業活動ですから、金価格が下がった時にはコスト割れしてまで採掘しません。ですから、金価格が1200ドルを割ると、約2割の金鉱山が減産するか生産を停止するわけです。 となると、金の供給量は減ってしまいます。 一方で需要に目を向けると、金価格が下がった時、上海・ドバイ・ムンバイの三大市場では現地の貴金属関係者が「こんなに売れているのに値段が下がっているのって不思議だよね。」といぶかるほど、金が飛ぶように売れていきます。 短期売買のニューヨーク(NY)先物市場が下げを主導しているのですね。これはプロの眼で「底値」のシグナルなのです。
事実、昨年、一昨年とNYの金価格が1200ドル以下にまで下がったことがありましたが、瞬く間に上昇に転じました。 安値圏内で生産は減り、需要は急増して需給が締まり、底値が形成されるわけです。
個人の意識が“守りの資産運用”にシフト |
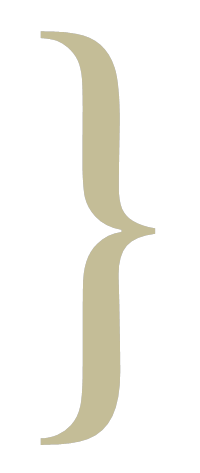 |
 |
金は株式などと違って底抜けしない。そこに個人投資家は安心感を得るのでしょう。実際、私がワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)という金の国際的調査機関に勤務していた頃に実施した調査では、日本人が金を購入した理由のトップは「無価値にならないから」というもので、これが全体の5~6割を占めました。こうした傾向は今でも変わっていないはずです。
前回、マイナス金利で一部の銀行が預金に手数料をかけることを検討しているという話をしましたが、かつてはサラリーマンの「お宝預金」と言われた社内預金も、厚生労働省が設定している最低金利(0.5%)を維持することが困難になり、実施する企業は3年前から2割減ったと報道されています。 マイナス金利やゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の不適切販売、さらには「年金だけでは老後資金が2000万円足りない」問題などが有機的に結びつき、個人マネーは“守りの資産運用”へと大きくシフトしてきました。 こうした動向は間違いなく金への資金流入を加速させています。
実際に足元、純金積立を始める人が急増しています。日本経済新聞でも、「各社の純金積立の口座開設数が例年を大きく上回るペースで伸びている」という報道がありました。 金価格が高値圏にある中で地金や金貨を購入するのはいわゆる“高値づかみ”になってしまうリスクがあります。今なら、積み立てという形でポートフォリオの一部に金を加えていくのは賢明な選択と言えるでしょう。

資産防衛手段としての金の強みは、底抜けしない需給構造にあり。
Text : Itsuo Toshima, Toshiko Morita
Illustration : Damien Florebert Cuypers
Artist Management:Agent Hamyak