
人生100年時代と言われている現在、資産運用への関心が高まっています。資産運用と聞くと「若い世代が取り組むもの」というイメージを持つ方もいらっしゃいますが、資産運用は定年後に始めることも可能です。
この記事では、定年後でも資産運用に取り組むべき理由やその際の注意点について詳しく解説します。
目次
- 定年後の資産運用でインフレへの備えに取り組める
- 資産運用は余裕資金で取り組み、上手にリスクをコントロールしよう
- 分散投資はリスクを軽減することにもつながる
この記事のポイント
資産運用は定年後からでも始められる?

定年退職は退職金などまとまったお金を手にするタイミングでもあります。すぐに使う予定がない場合は一部を資産運用にあてる方法があるものの「今から資産運用を始めるなんて遅いのでは?」と感じる方も少なくありません。
しかし、ゆとりあるセカンドライフを送るためには資産運用は不可欠とも言えます。まずは定年後に資産運用に取り組むべき理由について考えていきましょう。
20年以上のセカンドライフを過ごすことも珍しくない
「今さら資産運用なんて…」と考えてしまい「資産運用するだけの十分な時間がない」と億劫に思っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、平均寿命が延伸している現在では、定年後に数十年間のセカンドライフを送ることも珍しくありません。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、2024年の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.10歳でした。1990年の平均寿命は男性が75.92歳、女性が81.90歳だったため、およそこの30年間で男女ともに寿命が延びていることが分かります。
また、同調査によると65歳の平均余命は以下のとおりです。
男性:19.47年
女性:24.38年
平均余命とは、ある年齢の人が平均してあと何年生きられるかということを示すものです。前述の調査結果を見ると、男女どちらも定年後に約20年間のセカンドライフがあることが分かります。定年後に資産運用に取り組むことは決して遅いことではないのです。
インフレリスクへの備えにもなるのでおすすめ
定年後の主な収入源は、公的年金となることが一般的です。公的年金の支給額は、その時の物価や現役世代の賃金水準に応じて毎年4月に改定される仕組みとなっていますが、実はインフレ分をカバーしきれていない場合があります。
2025年度の公的年金支給額は前年度から1.9%の引き上げが行われていますが、物価の上昇率は2.7%となっています。要するに、0.8%以上の資産運用に取り組まないと、貯蓄を取り崩していくことになります。こうした背景から、年金の支給額は実質的に目減りしており、年金だけでは安心して暮らせないケースが出てくると考えられています。
このようなインフレリスクに備えるために、定年後も余裕資金の一部を資産運用にあてることが有効な対策です。
例えば、インフレ対策として純金積立を始めるのもひとつの方法です。金は実物資産であることから、価格が物価に連動しやすい傾向にあり、インフレから資産を守る投資先として知られています。
純金積立は少額からでも始められるため、インフレリスクへの備えとして検討するのも選択肢のひとつです。
定年後の資産運用で気をつけたいポイント

ここでは定年後に資産運用を行う際に、気をつけたいポイントについてご紹介します。
突発的な支出に備えるお金を確保する
定年後の資産運用に取り組む際は「どれくらいの金額を運用に回すか」ということを慎重に考えなければなりません。
一般的に定年後は現役時代に比べて収入が減る傾向にあります。また、自宅のリフォームや医療・介護などで大きな支出が発生することも考えられるため、あらかじめ緊急時に備えるための一定の余裕資金を確保しておくことが重要です。そうした備えをしながら、無理のない範囲で資産運用に取り組むことが大切です。
自分のリスク許容度を正しく理解する
一般的に定年後は収入が減る傾向にあることから、今手元にある資産を守っていくことが大切です。そのため資産運用に取り組む際は、ご自身のリスク許容度を正しく理解しておきましょう。
リスク許容度とは「どれくらいの価格変動を受け入れられるか(損失にどれだけ耐えられるか)」という目安です。リスク許容度を理解する時の主なポイントはご自身の資産額・年齢・投資経験や性格などですが、このリスク許容度が明確になっていないと、想定よりも値動きが大きな商品に投資してしまうことになりかねません。
余裕資金が潤沢にある場合は、一部を積極的に運用することも可能ですが、定年後の資産運用においてはリスクをなるべく抑えながら運用する方が適切と言えるでしょう。
長期的な視点で取り組む
最近はお金をたくさん残すよりも、うまく使いきってセカンドライフを謳歌するという考え方が広がりを見せています。セカンドライフが20年ほどあることを頭の片隅に置きながら「ゆっくり資産を育てつつ、上手に使っていく」という意識で取り組むのもひとつの手です。
そのためには長期的な視点で資産運用に取り組むことが重要です。もちろん短期的な値上がりによって年間の目標リターンをすぐに達成した際は早々に利益を確定しておくという戦略がありますが、相場に一喜一憂して売買を繰り返していると、いつの間にか損失が膨らんでしまうことも考えられますので注意が必要です。
現役時代とは異なり、収支のマイナスを収入増で補うのは難しく、急な支出には貯蓄で対応せざるを得ないケースがあるかもしれません。例えば、環境や体調の変化によって想定外の支出や運用計画の見直しが求められることもあります。そうした事態に備えるためにも、必要な時に手元に現金を用意できる仕組みである純金積立などで資金をある程度確保することも肝要です。
定年後の資産運用はリスク分散が重要

定年後の資産運用において、リスク分散に取り組むことも重要です。ここでは特に心がけたい「投資先の分散」と「時間の分散」の2つについて紹介していきましょう。
投資先を分散する
資産運用に取り組む際は、投資先を複数に分散することをおすすめします。複数の投資先に分散することで、価格が下落した時のリスクを抑えることができるためです。
まとまった退職金を受け取った方は、投資先をひとつに絞るケースも少なくありません。しかし、このような投資方法では、価格が下落した際に自分の資産の価値も大きく下げてしまうおそれがあります。リスクを軽減するためには、値動きの異なる複数の投資商品を組み合わせることを検討してみましょう。
時間を分散する
資産運用と言うと「まとまった金額を一度に投資する」というイメージを持つ方もいらっしゃることでしょう。確かにそのような方法もありますが、一度にまとめて投資する場合、価格の値動きを見極めながら、適切なタイミングを判断する必要があります。但し、ご自身で適切な買い時を判断するのはかなり難しく、もしタイミングが外れてしまうと「高い時に投資してしまった」ということにもなりかねません。こうした「高値づかみ」を避けるためには、積立投資を活用することが有効です。
積立投資とは定期的に一定額ずつ投資商品を買い付ける方法です。この方法はドルコスト平均法と呼ばれており、主に純金積立などで用いられ、時間を分散しながら投資できるメリットがあります。自動的に一定額を買い付けていくため金価格が高い時は少なく、安い時は多くの金量を購入することになり、結果として購入単価を平準化することができます。「いつが買い時なのか分からない」と迷う初心者の方にも取り組みやすい方法です。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
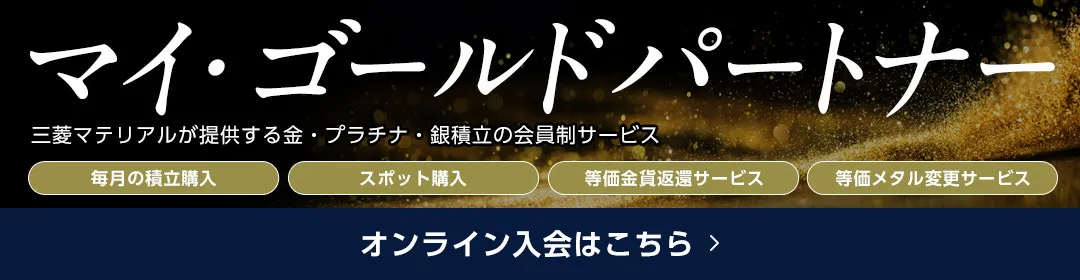
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
より豊かなセカンドライフを送るためには、定年後も資産運用に取り組むことが大切です。「今から始めるなんて」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんとリスク分散しながら取り組むことで、年齢やライフプランに見合った運用を行うことができます。
まずは、少額から始められる純金積立を取り入れてみてはいかがでしょうか。
※本記事は更新時の情報です




