
安全資産は元本が保証されている資産や目減りするリスクが低い資産を指します。一方、リスク資産は価格変動の幅が大きく、大きなリターンが狙える反面、大きな損失を被るおそれがある資産のことを指します。
投資する際は安全資産とリスク資産のバランスを意識することが大切です。今回は安全資産とリスク資産の違いやそれぞれの代表的な商品などを解説します。
目次
- 元本割れを防ぎたいお金は安全資産、積極的に増やしたいお金はリスク資産に投資するのが適切
- ご自身のリスク許容度に合わせて安全資産とリスク資産のバランスを考えることが大切
- 純金積立は安全資産である金を少額から積立購入できる投資方法
この記事のポイント
安全資産とリスク資産の基本的な違い

まず、安全資産とリスク資産の基本的な違いから解説します。それぞれの違いを把握した上で「どの資産を、どの程度購入するか」を判断する際の参考にしてみてください。
安全資産の特徴
安全資産とは経済状況や市場が不安定な状況になっても価値が変化しにくい資産を指します。安全資産の主な例として預貯金や国債、金が挙げられます。
例えば、預貯金は元本保証されているため、お金を保管したい時の預け先として適しています。国債は国が発行する債券です。主要先進国の国債は新興国と比べてデフォルト(債務不履行)になる可能性が低いとされているため、安全に保有できる資産として知られています。
金もそのものに価値のある「実物資産」であり、かつ埋蔵量が限られている希少な貴金属です。全世界で金の価値は共通しており、これまで無価値になったことがないため、長期的に安心して保有できる安全資産と言えるでしょう。「有事の金」と言われることもあり、国際情勢が不安定化した時やインフレによって通貨価値が下落している時に多くの投資家から購入されるのも金の特徴のひとつです。
リスク資産の特徴
リスク資産とは市場の変動によって価値が大きく動く可能性がある資産のことです。高いリターンが期待できる一方、損失が大きくなるおそれもあります。リスク資産の例として挙げられるのが株式や社債、不動産です。暗号資産(仮想通貨)もリスク資産に含まれるでしょう。
資産を大きく増やすためには運用資産にリスク資産を含める必要があります。しかし、リスク資産への投資配分を大きくしすぎると、自分のリスク許容度を超えてしまうおそれがあるため注意が必要です。投資する際は自分のリスク許容度や投資目的に応じて、安全資産とリスク資産のバランスを考えることが大切です。
それぞれの資産のメリット・デメリット

安全資産とリスク資産はそれぞれメリットとデメリットが異なります。
安全資産のメリット・デメリット
預貯金や個人向け国債は基本的に元本保証されています(※外貨預金は外貨建てでは元本保証されているが、為替の影響を受けるため円に換算すると元本割れのおそれあり)。当面の生活費や近い将来に使う予定があるお金など、確実に守るお金の保管先として適しているでしょう。
金は元本割れのおそれはありますが、世界中で普遍的な価値が認められていることが特徴です。長期的に価値を保全することが期待できるため、安心して保有し続けることができるでしょう。
金投資の方法はいくつかありますが、純金積立であれば少額から金を積立購入できるため、初心者の方でも取り組みやすい投資方法と言えます。
なお、安全資産のうち預貯金や個人向け国債は大きなリターンが期待できないため、インフレリスクに弱いのがデメリットです。
例えば、年間で3%のインフレが起こると貨幣価値は3%下落することになります。この場合、少なくとも毎年3%以上の利回りで運用できないと保有資産の価値を維持できません。安全資産の保有割合を高め過ぎると知らない間に資産が目減りしてしまうこともあるため注意が必要です。
リスク資産のメリット・デメリット
投資の世界では「ハイリスク・ハイリターン」と「ローリスク・ローリターン」という考え方が基本です。リスク資産は市場の成長や経済の拡大に伴って、高いリターンを得られる可能性があります。一般的にリスク資産へ投資する場合でも長期投資を行うことで安定した収益を得られると言われています。
ただし、リスク資産は市場の変動に影響されやすいため、価値が急激に減少するおそれがある点に注意が必要です。経済状況の悪化や政治や国際情勢の不安定化によって大きな損失につながることがあります。
効果的な資産配分の方法

投資する時に意識したいのが「分散投資」です。さまざまな資産にバランス良く投資することで、リスクを抑えつつ、かつ安定的に資産運用ができると考えられています。
年齢や目的によって配分を考える
一般的に若年層はリスク資産への投資割合を高め、高齢になるにつれて安全資産の投資割合を高めるのが適切とされています。高齢になるほど運用できる期間の確保が難しくなり、損失が発生した時のマイナス分を取り戻す機会が限られるからです。
ただし、「何歳の人はこのような資産配分にすれば良い」といった明確な正解は存在しません。資産状況やリスク許容度、運用目的などに応じて適切な資産配分は異なります。
実際に投資を始めた後は定期的な「リバランス」が不可欠です。リバランスとはポートフォリオの割合が計画からずれた際に元の比率に戻すことを指します。定期的にリバランスを行い、投資を始めてからある程度の期間が経過した際は、その時の資産状況やライフステージ、今後起こり得るライフイベントなどを鑑みて、ご自身にとって適切な資産配分を見直しましょう。
市場の動きを見て調整する
運用状況は市場の動きによって変化します。市場の不確実性が高まっていると判断した場合、リスク資産の保有割合を下げて、安全資産の保有割合を高める方法が考えられます。
例えば、株式の積立購入金額を引き下げて、純金積立への金額を増やす方法が考えられます。市場が不安定化するとリスク資産の値動きの幅は大きくなりやすいため、安全資産の保有割合を増やすことで精神的な負担を軽減できるでしょう。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
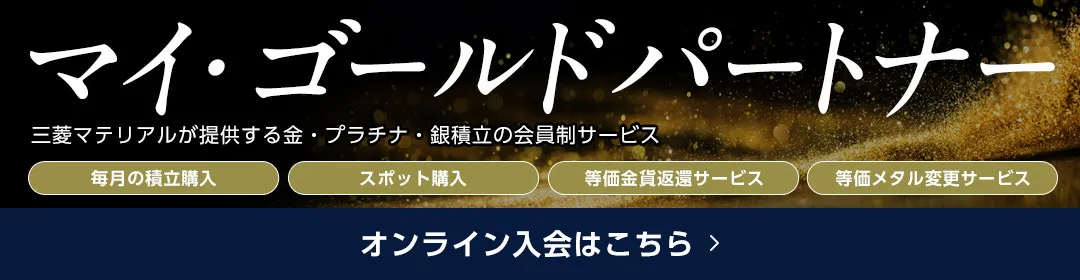
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
安全に資産を保有したい場合は預貯金や金などの安全資産へ、大きなリターンを狙いたい場合は株式や不動産などのリスク資産への投資がおすすめです。安全資産への投資を検討している方は純金積立も検討してみてはいかがでしょうか。少額から始めることができ、投資初心者の方でも取り組みやすい投資方法です。
安全資産とリスク資産の資産配分を考える時は、年齢や投資目的、リスク許容度などを踏まえて検討することが大切です。また、実際に投資を始めた後も市場の変化やご自身のライフステージの変化などに応じて適宜見直すことも欠かせません。ご自身にとって適切なバランスで資産を保有することを心がけましょう。
※本記事は更新時の情報です




