
金を保有している方の中には「いずれは子どもへ贈与・相続したい」と考えている方も少なくありません。しかし、その際に知っておきたいのが税金の仕組みです。この記事では親から子どもへ金を受け継ぐ際の贈与税・相続税の仕組みについて解説します。
※贈与税および相続税につきましては、所轄の税務署または税理士にご相談ください(税理士法第52条では、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」と規定されており、弊社が税務相談に応じることはできません)。
目次
- 将来的な価値上昇が期待できる金は資産承継の手段にも向いている
- 贈与を行う際は税制の理解が必要不可欠
- 金は相続税対策として活用することも可能
この記事のポイント
金の贈与の基本的なポイント

まずは金を贈与する際に知っておきたい基本的なポイントについて学んでいきましょう。
金の贈与のメリットを理解する
親から子どもへ資産を贈与する場合、最も願っていることは「将来、生活に困らないようにしてあげたい」という思いではないでしょうか。
贈与は現金で対応する場合が多いですが、現金はインフレに弱い資産です。例えば「将来お金に困ったら使って欲しい」という思いを込めて子どもへ現金を贈与しても、その後インフレによって物価が上昇すると子どものために贈与した現金の価値が目減りしてしまいます。
一方、金は長期的に資産価値を維持しやすく、インフレにも強い特徴があるため、親から子どもへのそのような思いを実現しやすい資産と言えます。また希少性が高い金は将来的に資産価値が上がる期待もできるため、親から子どもへ受け継ぐ資産として大きなメリットがあると言えるでしょう。
贈与方法について理解する
金は保有している金地金(インゴット)であればそのまま贈与することもできますが、「少しずつ贈与したい」、「一気に贈与すると税金の負担が気になる」という方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に備えて、別途手数料はかかりますが100g以下の金地金を購入しておくのも良いでしょう。三菱マテリアルでは100gのほかに5g・10g・20gの金地金をご用意していますので、用途にあわせてお選びいただけます。
また、純金積立では積み立てた金の一部を現物で引き出して贈与することもできます。そのため金地金のように分割する手間や費用がかからないのは大きな魅力です。
贈与税に関する重要ポイント

金を贈与する時に知っておきたいのが贈与税の仕組みです。ここからは贈与税の考え方や注意点について確認しましょう。
贈与税の基本的な仕組み
金を贈与した時は「贈与税」の対象となり、課税の対象となります。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、贈与を受けた資産の合計が年間110万円以下であれば贈与税は発生しません。なお、この「年間」とは1月1日〜12月31日を指します。贈与を行う方の中には年末に行うケースが多く見られますが、年を跨がないように注意しましょう。
金の贈与における注意点
金を贈与する際に注意すべきポイントがあります。それぞれ確認しましょう。
金の評価額は「贈与日の時価」
金を贈与する際、その評価額は「贈与日の時価」によって贈与した金額が算出されます。例えば「控除額に収まるように贈与したい」と考えて準備しても、贈与日に金価格が上昇していれば控除額を超える可能性があります。控除額を超えた分は課税対象となりますので、その際は申告漏れがないように注意しましょう。
定期贈与とみなされる可能性がある
先程年間110万円以下の贈与であれば税金がかからないと解説しましたが、この時に知っておきたいのが「定期贈与」とみなされる場合です。
毎年基礎控除の範囲内で贈与を行っていても、毎年一定の金額を贈与する「定期贈与」と判断されれば、贈与税の対象となることがあります。例えば「毎年100万円分の金を10年間贈与する」とした場合、年間の基礎控除内に収まっているので一見税金はかからないように感じられます。しかし、税務調査が入った際など「最初から1,000万円分を贈与するつもりだった」とみなされると贈与税の対象となる可能性があります。
そのため、贈与を行う際にはたとえ親子間であっても贈与を行うごとに「贈与契約書」を作成しておくことを検討しましょう。贈与契約書とは贈与が行われたことを証明するための書類であり、後になって「いつ、いくらの贈与を行ったか」ということを振り返る際にも役立つ書類です。相続が発生した時にトラブルを防ぐ役割があるため、贈与を行う時はきちんと贈与契約書を作成しておきましょう。
金を活用した相続税対策のポイント

金は相続税対策としても有効な手段です。ここからは相続税対策のひとつとして金を活用する際のポイントをご紹介しましょう。
生前に贈与するメリットと注意点を理解する
相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数) ※」の基礎控除があります。仮に配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、4,800万円が基礎控除額です。相続による資産がこの控除額を超える場合、相続税の対象となり、相続人が税金を支払わなければなりません。
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで
もし、現時点で基礎控除を超える可能性がある場合、生前から資産を贈与し、相続資産を圧縮しておく方法が有効と言えます。先程ご紹介した金の贈与のように少しずつ資産を受け継ぐことを検討すると良いでしょう。
ただし、その際に気をつけたいのが「生前贈与加算」です。生前贈与加算とは、相続が発生した時に、被相続人(亡くなった人)から一定期間内に生前贈与を受けた資産については、贈与税がかかったかどうかに関係なく、その資産を相続資産とみなすものとなっています。従来は「相続開始前3年以内」の生前贈与が加算対象となっていましたが、法改正が行われ加算対象が7年以内へと引き延ばされています。現在は段階的に適用されていますが、2031年1月1日以降は「相続開始前7年以内」の贈与が相続資産へと加算される仕組みとなります。
そのため相続税対策として生前贈与を行う際は早いうちから計画的に取り組むことが大切です。
将来を見据えた計画を立てておく
将来値上がりが見込まれる金を贈与する場合、「相続時精算課税制度」を活用するのもひとつの方法です。相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の父母または祖父母」から「18歳以上の子または孫」に贈与する時、2,500万円までは贈与税がかからない制度を指します。その代わり贈与した資産は相続が発生した時に相続資産へ持ち戻して相続税が算出される仕組みです。
相続時精算課税制度は原則贈与を行った日の価額で相続資産へと持ち戻されます。ここではさらに分かりやすく具体例で考えてみましょう。
相続時精算課税制度を使って2,000万円分の金を贈与したとします。その後、金価格が上がり、相続が発生した時には2,500万円まで価値が上がりました。この時相続税の算出対象となるのは当初贈与した時点の評価額である「2,000万円(※相続時精算課税の基礎控除は考慮せず)」です。つまり贈与後の値上がり分には相続税が課税されません。
このように将来的に値上がりが予想される資産は相続時精算課税制度を活用して早めに贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性が見込まれます。ただし、逆に相続時に値下がりしていれば税負担が大きくなることや一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税が行えなくなる点には注意が必要です。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
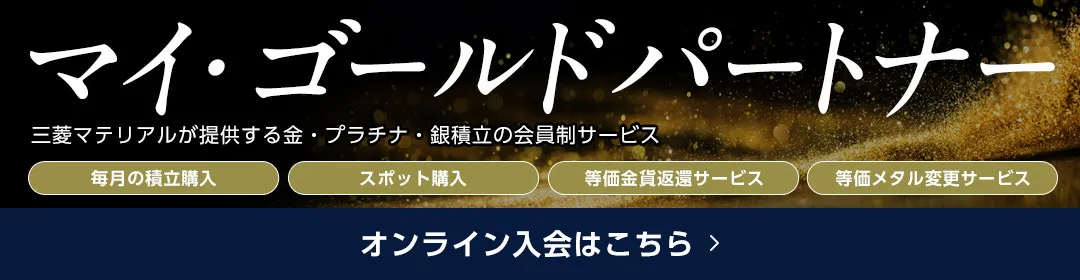
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
金の贈与は長期的に価値を保ちやすい資産を子どもへ残せるメリットがあります。また、相続税がかかることが予想される場合は、早いうちから計画的に生前贈与を行っておくことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。次世代への資産承継のひとつとして、金での資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事は更新時の情報です




