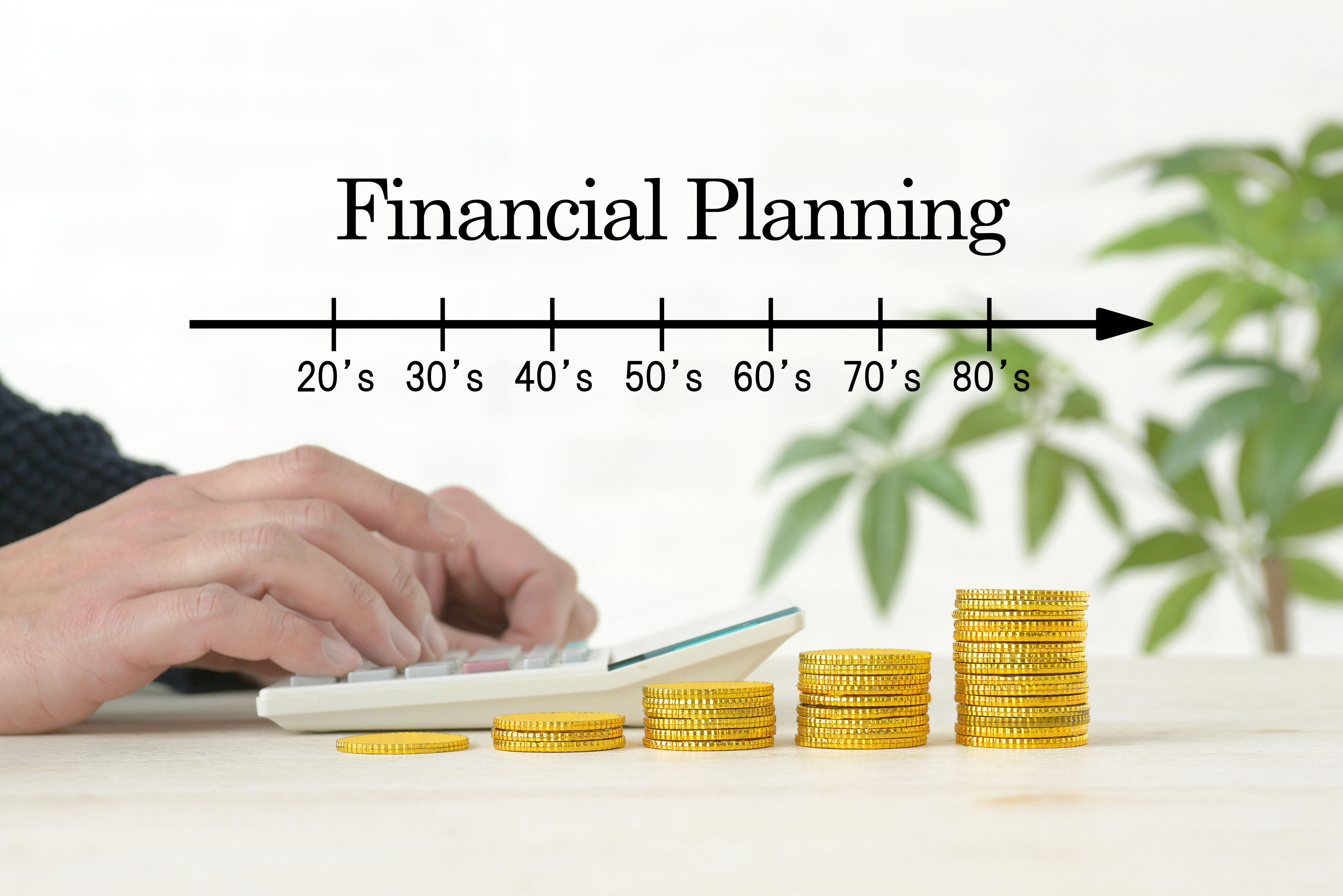
一般的に30代は将来に向けた資産形成を考える方が増える年代と言われています。預貯金だけでは効率的に資産を増やせないと感じているのであれば、資産運用が選択肢のひとつとなるでしょう。
しかし、初めて資産運用をする方は「どのようにすれば良いのか」、「どのような商品を買えば良いのか」など、迷うことがあるかもしれません。そこで今回は30代の方が資産運用を始めるべき理由や具体的な運用方法などを解説します。
目次
- 30代はライフイベントが多く、資産運用を始めるのに適した時期である
- 30代は資産運用期間を長期間確保できる強みがある
- 資産運用の方法のひとつとしておすすめなのが純金積立
この記事のポイント
30代からの資産運用、まだ間に合う?

現在は「人生100年時代」と言われるように、30代の方の多くはこの先50年以上生きると見込まれています。そこで30代の資産運用の特徴と30代でスタートするメリットについて見ていきましょう。
30代の資産運用の特徴
一般的に30代は結婚や子どもの誕生、マイホームの購入など、いくつかのライフイベントを迎える年代です。ライフステージを考えると短期的に必要なお金を確保したり、中長期的にお金を用意する計画を立てたりする必要があります。
計画的にお金を用意できなかったことで、理想としている生活ができないこともあるでしょう。このようにならないためにも家計管理をした上で投資に回せるお金を把握し、リスク許容度の範囲内で投資を始めましょう。また、家計を分析して無駄な支出を削減し、家計の健全度を高めることも大切です。
なお、金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、30代の総世帯における金融資産平均保有額は604万円でした。
各投資商品の平均保有額は下表のとおりです。
| 金融資産保有額 | 604万円 |
| 預貯金(運用または将来の備え) | 299万円 |
| ┗うち定期性預貯金 | ┗58万円 |
| 金銭信託 | 6万円 |
| 生命保険 | 39万円 |
| 損害保険 | 6万円 |
| 個人年金保険 | 23万円 |
| 債券 | 12万円 |
| 株式 | 109万円 |
| 投資信託 | 91万円 |
| 財形貯蓄 | 12万円 |
| その他金融投資商品 | 7万円 |
出典:金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」
割合が最も多かったのが預貯金ですが、次いで株式や投資信託が多く、30代では保有資産の一部を資産運用に充てていることがうかがえます。20代の金融資産平均保有額が212万円であることを踏まえると、30代では20代よりも資金に余裕が生まれることで、資産運用を取り入れる動きが強まっていると考えられます。
30代からスタートするメリット
一般的に日本の企業は年齢が上がるにつれて収入が増える傾向です。役職に就いている方であれば、平均よりも高い収入を得ている場合もあります。30代は20代と比べると経済的な余裕が生まれやすいため、資産運用を始めるには適切なタイミングと言えるでしょう。
また、一般的に資産運用は期間が長くなるほどリスクを軽減でき、リターンが安定すると考えられています。長寿社会の現在、30代の方であれば50年以上の運用期間を確保することもできるため、資産運用に取り組みやすい年齢層と言えるでしょう。
更に、資産運用を通じて資金計画を立てることができれば、将来のライフプランの見通しがしやすくなるのは大きなメリットです。例えば、教育資金やマイホームの購入など大きな支出に備えて運用を行えば、無理のない生活設計を立てることができます。
30代におすすめの資産運用方法

30代の方が資産運用する場合、ある程度リスクを取った運用をされている方も少なくありません。しかし、中には「最初は怖いからリスクを抑えたい」という方もいらっしゃるでしょう。ここでは安定性重視、収益性重視の運用プランをご紹介します。
安定性重視の運用プラン
安定性を重視したい場合は資産運用に回す金額を抑えつつ、比較的リスクが小さい投資商品を選択すると良いでしょう。例えば債券を購入したり、株式や債券にバランス良く投資できる投資信託を購入したりする方法が考えられます。
また、金への投資もひとつの方法です。金は世界中で取引されており、戦争や紛争、政情不安などの際には投資家がリスク回避の手段として金を購入する傾向があり、「有事の金」とも呼ばれています。さらに、実物資産のため無価値になるリスクがほとんどありません。
加えて、価格変動リスクを軽減するためには毎月一定の金額を設定して金を定額購入する純金積立が選択肢のひとつとなるでしょう。
収益性重視の運用プラン
ある程度リスクを取って収益性を重視したい場合は株式投資や不動産投資を検討すると良いでしょう。実物の不動産を購入するのではなく、証券化されたREIT(不動産投資信託)を購入する方法もあります。
投資対象となる資産の中でも一般的に株式はハイリスク・ハイリターン、不動産はミドルリスク・ミドルリターンと言われていますが、不動産投資も対象物件や市況によっては価格変動が大きくなる場合があり、株式と同様に高い収益性を期待できます。
ただし、リスク管理の観点を忘れてはいけません。大きなリスクを取れば取るほど市場変動によって運用している投資商品が大きな損失を抱えるおそれがあります。
そのためリスクが高い商品に投資しながら、純金積立のようなリスクが低い投資商品も併用するのが適切です。バランスの良いポートフォリオを組めば、リスクの高い商品に投資をしつつ資産運用全体のリスクを抑えることができます。
30代からの具体的な始め方

資産運用が未経験という方は具体的にどのような手順で取り組めば良いのか分からないこともあるでしょう。以下では資産運用の具体的な始め方を解説します。
初期投資のステップ
まず、詳細な生活設計を立て、いくら投資に回しても問題ないか、運用資金を検討しましょう。運用資金は生活に支障をきたさない範囲で決めることが大切です。
次に、ご自身のリスク許容度を把握した上で、実際に投資する商品を見極めましょう。投資商品を選ぶ際には購入を検討している商品にどの程度のリターンが期待できるかを確認し、ご自身が求めているリターンに見合うかを判断しましょう。
また、投資商品にどのようなリスクがあるか認識することも欠かせません。「不況時には最大で○%価値が下落する可能性がある」というように具体的な数字で把握しておくと安心です。
長期的な資産形成のコツ
リスクを抑えて安定的にリターンを求めるには長期的な運用を意識することが大切です。例えば、資産運用を継続するのにおすすめなのが積立投資です。積立投資は毎月積立購入することを前提とする投資方法ですので、長期的な運用を目的とする方に向いています。また、購入するタイミングが分散されることで価格変動リスクを軽減する効果を期待できます。
自動積立の仕組みが用意されていることが多いため、「毎月〇万円を積立購入する」のように一度設定しておくと、毎月自動的に投資が行われます。このように自動的に積立投資されるので、手間がかからないこともメリットです。
また、長期的にリターンを安定させるためにはさまざまな資産に投資先を分散することも重要です。例えば、投資信託を購入すれば、国内外の株式や債券などに簡単に分散投資することができます。加えて、金などの実物資産にも投資することでより大きな分散効果を得ることができます。
純金積立は少額から始められ、リスク分散が期待できる長期的な資産形成方法です。ドルコスト平均法で購入価格が平準化される点も大きな魅力です。金は世界共通の価値を持っているので、分散投資先のひとつとして純金積立を検討してみてはいかがでしょうか。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
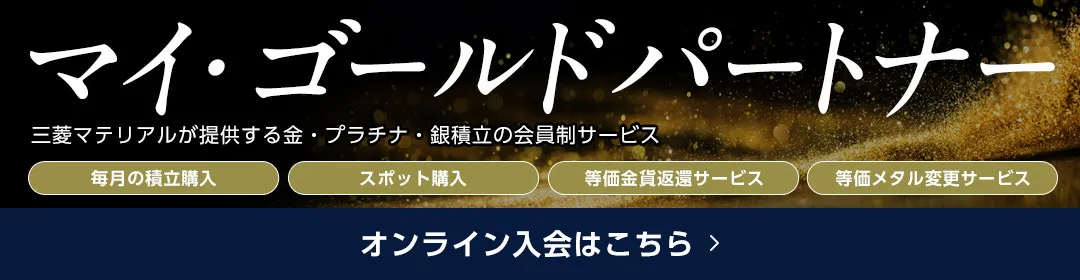
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
30代の方は長期的に資産運用に取り組みやすい年代と言われているため、早い段階で資産運用を始めると良いでしょう。運用方法はご自身の資産状況や価値観、性格などによって異なります。また、安定性を重視するのか、収益性を重視するのかによっても運用方法は異なりますのでご自身に合った有効な方法を検討しましょう。
資産運用には元本割れのリスクが伴うためリスクの取り過ぎは禁物です。自分が投資に回しても問題ない資金を把握した上で長期的に運用と向き合いましょう。
「できるだけリスクを抑えて資産運用したい」という方におすすめなのが純金積立です。安全資産である金を少額から着実に購入できるため安定性を重視する方に向いています。
分散投資の一環としても効果を期待できるので、資産運用を始める際には選択肢のひとつとして純金積立を検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事は更新時の情報です




