
労働所得とは労働の対価として受け取る給与や報酬のことです。一方、資産を保有していることで得られる所得を資産所得と呼び、働かずに得られる所得とも考えられます。資産所得が増えるほど生活にゆとりを感じられるでしょう。そこで本記事では労働所得と資産所得の違いや資産所得を増やすためのポイントなどをご紹介します。
目次
- 労働所得以外に資産所得があれば経済的なゆとりが生まれやすい
- 資産所得を得るには金融資産か実物資産を購入する必要がある
- 投資初心者の方には少額から始められる純金積立がおすすめ
この記事のポイント
労働所得と資産所得の違いとは?

労働所得とは「自身の身体や時間」を使って得られる所得であり、資産所得は「個人が持っている資産」を使って得られる所得です。ここではそれぞれの所得の特徴や資産所得を得る意義などを見ていきましょう。
それぞれの所得の特徴
前述のとおり、労働所得とは労働によって得られる収入のことです。労働者としてのスキルや知識、時間を提供し、その対価として受け取る収入をイメージすると分かりやすいでしょう。労働所得は主に2つあり、会社員や公務員が勤務先から得られる賃金や賞与などは「給与所得」、事業主としてその事業から得る所得は「事業所得」となります。
一方、資産所得とは基本的に労働を伴わない状態で、資産を保有することで得られる収入であり、「不労所得」とも呼ばれます。主に預貯金や債券から得られる利息を受け取った時の利子所得、株式から得られる配当所得、家賃収入である不動産所得が挙げられます。
このように労働所得は個人の労働力が資本であり、資産所得は保有している資産が資本です。労働所得は働くことで得られる所得のため働き続けることができれば比較的安定しています。一方で資産所得は市場変動の影響を受けるため不安定になる場合があるでしょう。
資産所得を得る意義
労働所得以外にも資産所得があれば収入の幅が広がります。資産所得を増やすことで自由に使えるお金が増えれば、その結果、人生の選択肢が広がります。また、もし何らかの事情で働けなくなった場合でも資産所得で補える可能性もあります。
さらに老後生活において公的年金に加えて、資産所得が上乗せになれば、豊かな老後生活を送れる可能性が高まるでしょう。
資産所得を得るための方法

資産所得を得るには所得を生み出す資産を保有する必要があります。資産には金融資産と実物資産がありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
金融資産からの所得
主な金融資産としては株式や債券が挙げられます。株式を保有している場合は配当所得を、債券を保有している場合は額面金額に応じた利息をそれぞれ受け取ることができます。これらはいずれもインカムゲインであり、家計に経済的なゆとりをもたらすでしょう。また、低金利が続いている状況下では得られる所得は限られていますが、預貯金から得られる利息も資産所得に含まれます。
実物資産からの所得
主な実物資産としては不動産や金・プラチナ・銀などの貴金属が挙げられます。
不動産投資で得られる家賃収入も資産所得であり、物件の価値が上がった場合には売却して利益を得られる可能性があります。
金は実物資産として、現物を購入する方法や定期的に積立購入する純金積立などの方法が代表的です。現物購入はまとまった資金が必要になりますが、純金積立は数千円程度から始められるため、まとまった金額を投資することに抵抗がある方や投資初心者の方に向いています。
資産所得の効率的な作り方のポイント

資産所得を得るためには資産を購入するためのお金を準備し、ご自身のリスク許容度に応じて適切な資産を選択して購入することが重要です。また、特定の資産を集中的に購入するのではなく、さまざまな資産をバランスよく購入することが重要です。ここでは資産所得の効率的な作り方のポイントを見ていきましょう。
ポートフォリオを考え、分散投資を意識する
ポートフォリオとは保有する投資商品の組み合わせのことです。預貯金・株式・債券・金・不動産などの資産を「どのような構成で保有するのか、または、保有しているのか」を確認する際に用います。ポートフォリオを考える場合は、自分のリスク許容度を確認することが重要です。リターンを優先するとその分リスクが高くなるため、想定以上の損失を受けてしまい、生活に支障が出てしまうおそれがあります。
また、投資商品を保有していれば、資産所得を得られる一方で、相場の状況次第では保有している資産が目減りするおそれがあります。しかし、さまざまな資産に分散投資していれば、資産所得を得つつ保有資産が減少するリスクを抑えることができます。
このほか長期的な資金計画を立てることも大切です。例えば資産所得を増やすために生活費を切り詰めてまで投資に回すのは適切ではありません。「得られる資産所得を少しずつ増やす」というスタンスで投資と向き合えば、過剰なリスクが生じることなく着実に資産所得を増やせるでしょう。
税制優遇制度の活用や専門家に相談する
資産所得を効率よく増やすためには税制優遇制度を活用するのもひとつの方法です。株式や投資信託などの金融資産から得られる所得には、通常20.315%の税金が発生しますが、NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、株式から得られる配当や投資信託から得られる分配金を非課税で受け取れることから、より多くの資産所得を得ることが期待できます。
必要に応じてFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)といった専門家に相談すれば、ライフプランの作成や投資計画の立案をサポートしてもらえます。ご自身に合った投資方法や投資対象の資産を相談したい時は、専門家に相談してみるのもひとつの方法です。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
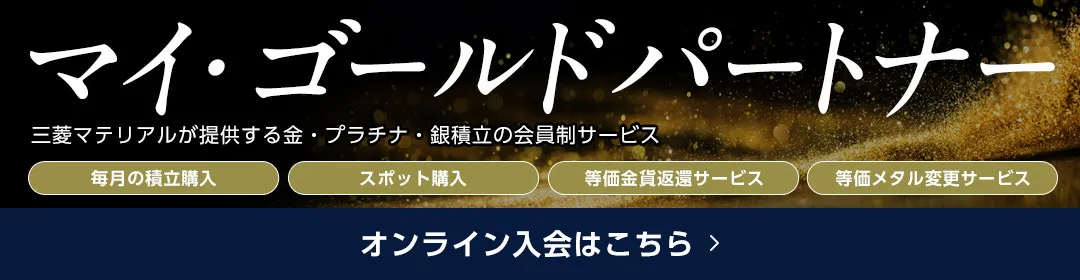
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
労働所得だけでなく、資産所得を得ることができれば、生活をより豊かなものにできるでしょう。預貯金だけでなく、株式・債券・金などさまざまな資産に分散投資することをおすすめします。
なお、安全資産である金への投資を検討しているのであれば、純金積立をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
金はその歴史において一度も無価値になったことがない強みがあり、分散投資先としても適しています。中でも純金積立は無理のない金額で投資を継続できるため、投資初心者の方の資産形成におすすめの投資方法です。
※本記事は更新時の情報です




