
投資する場合、適切な資産の配分を決めておくことが大切です。とは言え「資産配分の考え方が分からない」、「どのような資産を組み合わせればいいのだろう?」と悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
ここでは資産配分の基本的な考え方や投資目的に基づいた配分方法について解説します。
目次
- 資産配分は自分の投資目的に応じて決めることが大切
- 分散投資の効果を高めるには純金積立も取り入れてみよう
- 資産配分は定期的な見直しが必要
この記事のポイント
投資における資産配分の基本

資産運用において「分散投資」が基本のひとつとして知られています。複数の資産に分けて投資することによってリスクを分散する効果が得られるためです。
では、実際に資産を分散する際はどのような点に注意をしたら良いのでしょうか。ここでは年代や目的別の資産配分の考え方についてご紹介します。
年齢による資産配分を考える
適切な資産配分は各年代によって異なります。例えば若年層が老後資金の準備を目的として投資に取り組む場合、長い運用期間を確保できるため、ある程度リスクを取った運用が可能です。もし大きな市場変動によって含み損が生じた場合でも運用期間が長ければ市場の回復を待てる余裕があるためです。
一方、セカンドライフが近づく年代では運用期間が限られるため、ある程度リスクを抑えた資産配分が適切と言えるでしょう。投資を行う際は自分のライフプランを考えた上で「どれくらいの運用期間を確保できるのか」という点を踏まえて資産配分を決定することが大切です。
投資目的を明確にし資産配分を考える
適切な資産配分は投資目的によっても異なります。例えば「10年後のマイホーム購入に向けて頭金を貯めたい」という方がリスクの高い資産に偏った運用をするのは適切とは言えません。いざ10年後に資金が必要となった場合、市場変動によっては元本を下回っている可能性があるためです。
反対に「30年後のセカンドライフに向けて積極的な資産運用に取り組みたい」という方がリスクの低い資産に偏った運用をすると期待する利回りを得られない可能性もあります。
資産配分を決める際は「なぜ資産運用に取り組むのか」、「そのためにどれくらいのリスクを許容できるのか」ということを明確にしておくことも大切です。
具体的な配分モデルを知る

資産配分の考え方を理解した上で具体的な資産の組み合わせ方を考えてみましょう。ここでは投資初心者向けの基本配分と経験者向けの応用配分について一例をご紹介します。
初心者向けの基本配分
初めて資産運用に取り組む際は「どうやって資産配分を決めれば良いのか分からない」と悩むこともあるでしょう。この時に参考のひとつとなるのがGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオです。
GPIFは年金積立金の運用・管理をしている機関です。厚生労働大臣が定めた2020~2024年度の「第4期中期目標」では、運用を通じて「賃金上昇率+1.7%」の利回りの達成を目指しています。具体的には下表の資産構成割合が基本ポートフォリオとなります。
| 資産 | 資産構成割合 |
| 国内債券 | 25% |
| 外国債券 | 25% |
| 国内株式 | 25% |
| 外国株式 | 25% |
出典:GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)第4期中期目標期間(2020年4月1日からの5カ年)における基本ポートフォリオを基に作成
このポートフォリオはGPIFが目標とする利回りを得るために最もリスクが小さい資産配分として選定されたものです。初めて資産配分を考える際はこのGPIFのポートフォリオを参考にしてみましょう。
また、よりリスクを抑えた運用をしたい場合は、このポートフォリオに純金積立を加えることを検討してみると良いでしょう。純金積立は毎月任意の金額を設定して金を積立購入する方法です。安全資産のひとつである金をポートフォリオに加えられるメリットがあり、株式や債券に加えて純金積立へ投資することで分散投資の効果を高めることが期待できます。
経験者向けの応用配分
投資経験が十分にあり、より積極的な運用を希望する場合は先程ご紹介したGPIFのポートフォリオをベースに株式の割合を高めてみることが有効です。GPIFのポートフォリオは株式と債券のバランスが1:1となっており「積極的な資産」と「守りの資産」を均等に組み入れた資産配分となっています。より積極的にリターンを追求したい場合は株式に比重を置きながらリスクを高めた資産配分を検討しましょう。
ただし、ハイリスク・ハイリターンの運用に取り組む場合であっても一部を守りの資産として組み入れることは欠かせません。資産の全てを株式のような変動が大きいもので運用した場合、将来起こり得る市場変動の影響で保有資産が大きく減少するおそれがあるためです。
積極的な資産運用に取り組む場合でも純金積立や債券など、株式と相関性の低いものを組み合わせながらポートフォリオを構築しましょう。
長期投資を成功させるポイント

資産運用に取り組む際は分散投資と合わせて「長期投資」も徹底することが大切です。しかし、いざ投資を始めてみると「目先の市場変動に振り回されてしまい、慌てて売却してしまった」というケースも珍しくありません。
長期投資を成功させるためにはどのような点に気をつければ良いのでしょうか。ひとつずつ確認していきましょう。
資産配分を見直す
長期投資に取り組むためには、定期的に資産配分を見直すことが大切です。資産配分のバランスは市場の動きとともに変化することがあるためです。例えば株式と債券のバランスを6:4で配分したとします。この時に株式市場が上昇するとともに保有資産の価値が上がると株式:債券のバランスが7:3または8:2へと変化します。このバランスを元に戻すためには株式を一部売却して債券を買い付けて調整することが必要となります。これを「リバランス」と言い長期投資に取り組む際には欠かせないステップです。適切な資産配分を保つためには「3か月に一度ポートフォリオを確認する」など投資のマイルールを定めておきましょう。
運用を継続してみる
投資を始めて日が浅い方にとって市場変動は大きな不安材料になります。市場は常に変動しており、時には大きく値動きを見せることも珍しくありません。しかし、その動きに振り回されて保有資産を売却すると資産を着実に育てることが難しくなります。
投資に取り組む際は長期的な視点を意識しながら目先の値動きに振り回されないよう心がけることが大切です。慌てて売却するのではなく、冷静に状況を分析し、ご自身の長期的な目標を再確認するようにしましょう。
純金積立なら三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナー
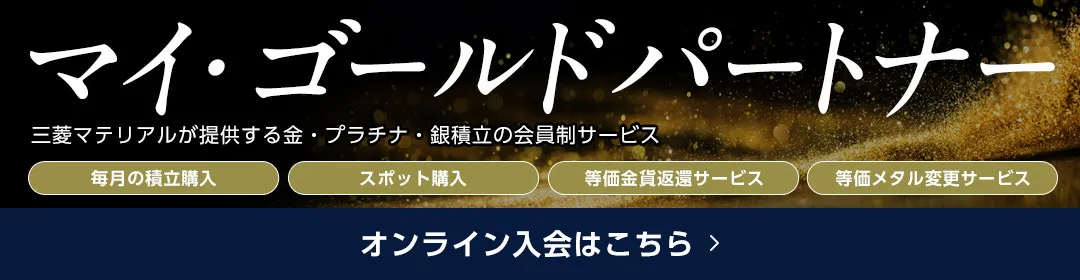
これから純金積立を始めようと考えている方は、大切な資産を安心して預けるためにも信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。
しかし「どこの運営会社を選べば良いのか分からない」、「さまざまな候補がありすぎて選ぶことができない」とお悩みの方には、三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーをおすすめします。
三菱マテリアルは明治29年(1896年)から100年以上にわたって金の製錬に取り組んできた歴史があり、国際基準の高い品質を保証しています。
マイ・ゴールドパートナーでは金だけではなくプラチナや銀の積立もでき、月々3,000円から無理のない範囲で積立購入ができるほか、年2回まで任意の月を指定して、月額積立購入金額に加算できるボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入にも対応しているため、ご予算に応じて無理なく購入できます。
年会費は800円、積立購入手数料は1,000円につき26円(消費税込)または31円(消費税込)、ボーナス月プラス積立購入や各種スポット購入の場合には手数料がかかりません。
保管料は消費寄託預かりでは無料、混蔵寄託預かりでは有料です。口座管理料はかかりません。
積み立てた金は金地金で現物を受け取ったり、金貨で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。
現物引出手数料は金地金1本あたり6,000円~7,500円(サイズによって異なります。500g以上の金地金は無料)。配送手数料は2,000円(保険料込)です。
オンライントレード(インターネット取引サービス)を利用すればお手軽に取引ができるため、買い時や売り時を逃すことも少ないでしょう。当社店頭価格より優遇※されたWeb価格が適用されます。
※Web価格は当社店頭価格に比べ、金・プラチナで10円/g、銀で0.15円/gの優遇となっております。適用対象はオンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスです。
詳細比較は以下ホームページ「マーケット情報・最新の価格」をご覧ください。
また「会員継続ボーナス」というユニークな特典があり、会員が会員契約期間開始日から会員契約期間満了日までマイ・ゴールドパートナーを継続してご利用いただいたことに対する特典として、会員契約期間満了日にお客様の消費寄託残高に加算します。
なお、金・プラチナ・銀の消費寄託、混蔵寄託の購入取引が対象です(混蔵寄託は金のみの取扱いとなります)。詳細は以下ホームページをご参照ください。
まとめ
資産運用に取り組む際は適切な資産配分を知っておくことが大切です。しかし、どのような資産配分が適切かはご自身の投資目的や運用期間などによって異なります。
まずは「なぜ資産運用に取り組むのか」、「どれくらいのリスクを許容できるのか」ということを明確にし、どの資産をどのようなバランスで組み入れることが適切かを考えてみましょう。
※本記事は更新時の情報です




